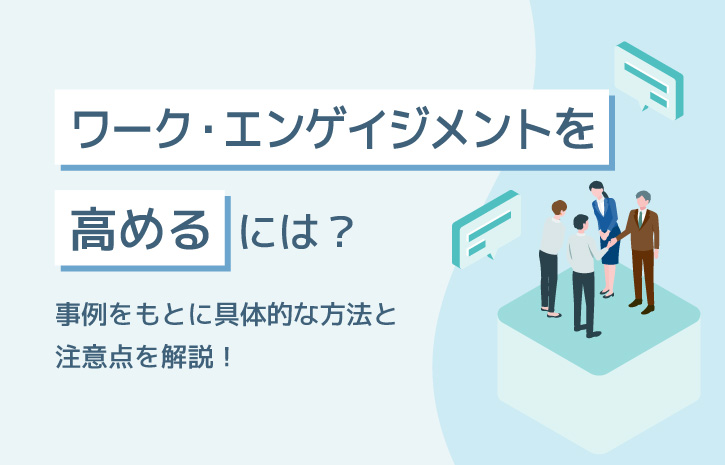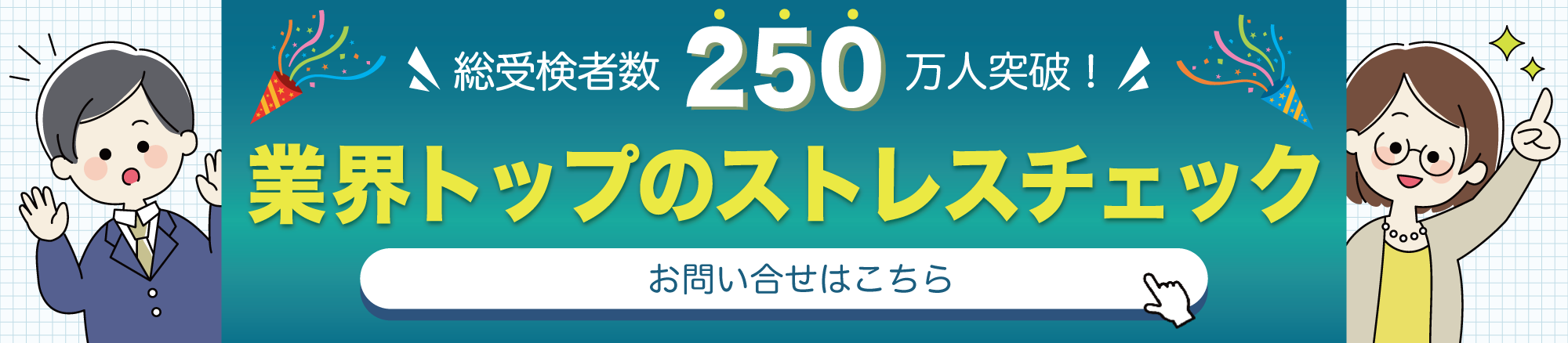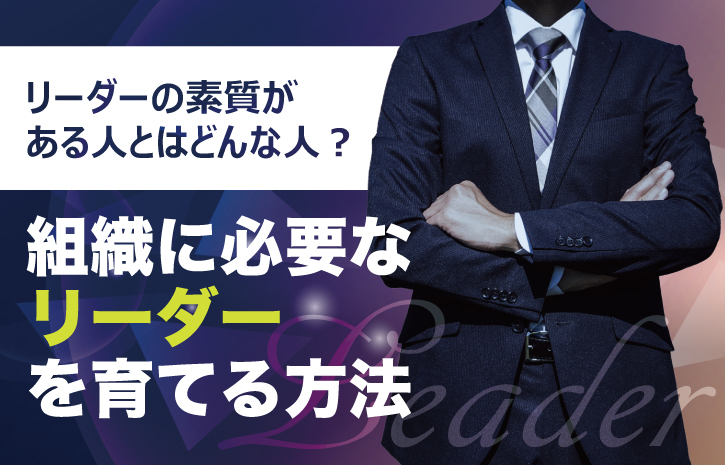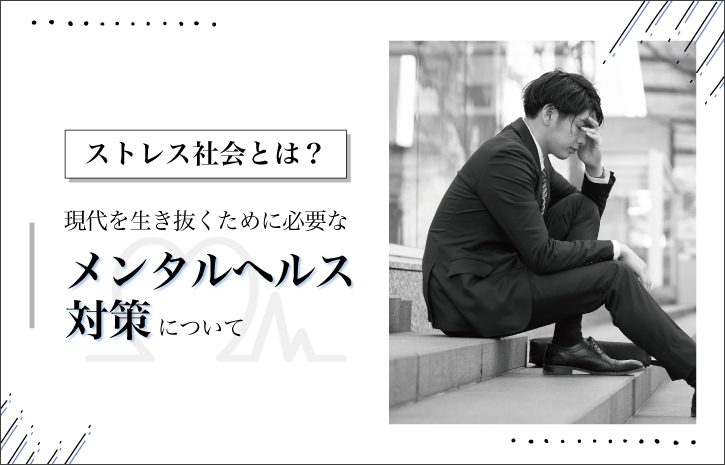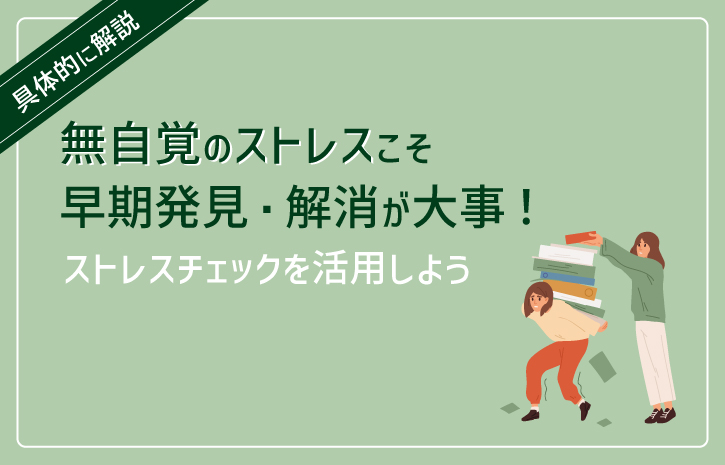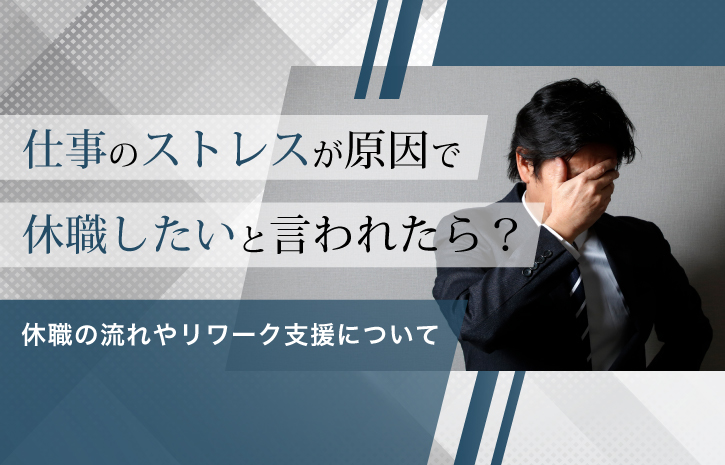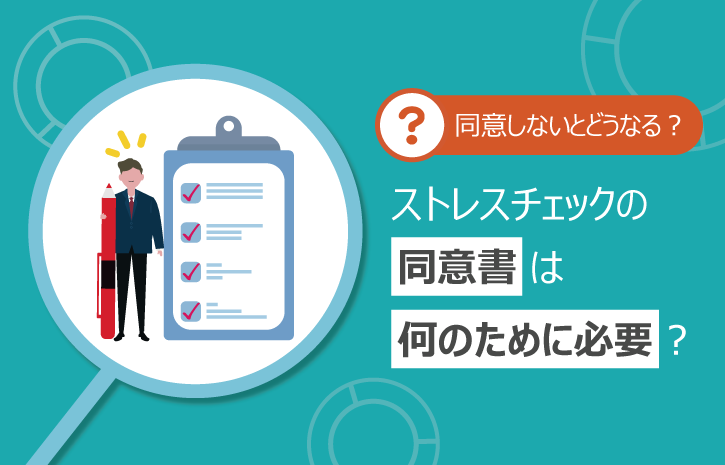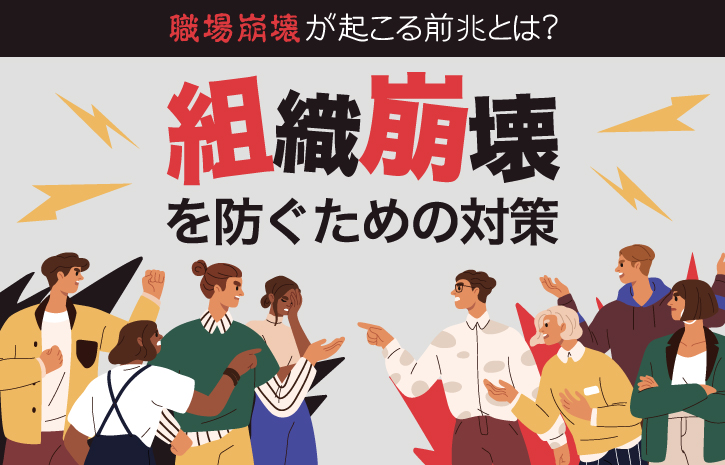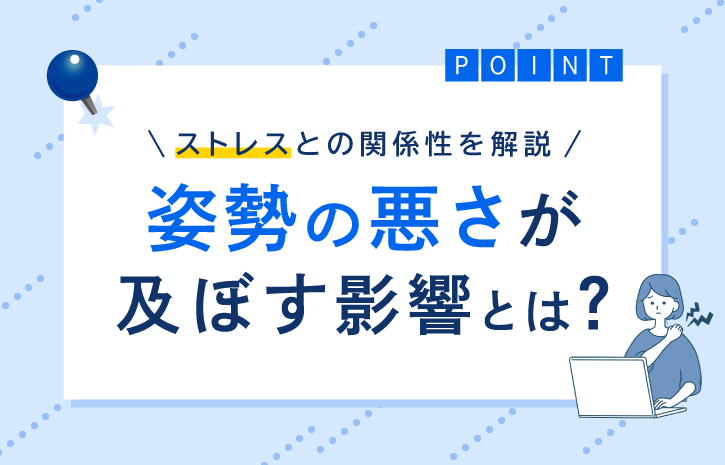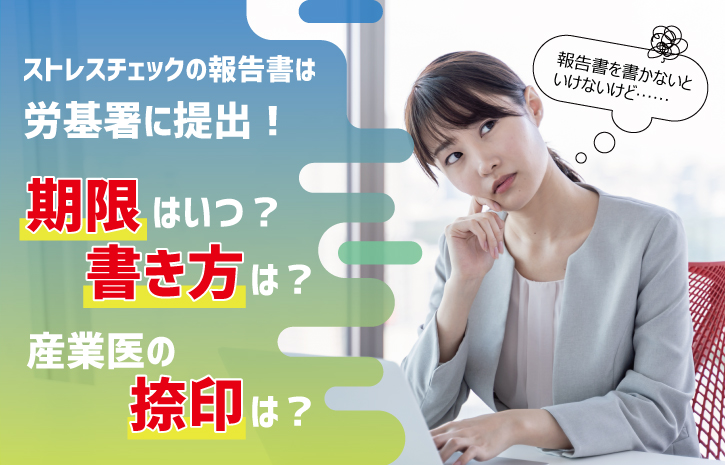ワーク・エンゲイジメントとは
ワーク・エンゲイジメントとは、仕事に対してポジティブで充実した心理状態を指します。
活力(Vigor)、熱意(Dedication)、没頭(Absorption)の3つの要素で構成されていて、従業員が仕事に積極的に関与し、仕事を通じて自己実現感を得ている状態を意味します。
ワーク・エンゲイジメントを高めるメリット
ワーク・エンゲイジメントを高めることで、以下のようなメリットが得られます。
これにより、従業員が仕事に主体的に取り組む意欲を高める、組織全体のパフォーマンス向上にも寄与します。
ワーク・エンゲイジメントを高める取り組み事例
事例①:参加型マネジメントの導入
課題:
従業員の意見が十分に反映されず、エンゲイジメントが低下。
取り組み:
参加型マネジメントを導入し、従業員が意見を自由に発言できる環境を整備。定期的なワークショップやオープンなコミュニケーションを通じて、従業員が組織の目標に共感しやすくした。
成果:
従業員エンゲイジメントが向上、組織全体のコミュニケーションが改善した。
事例②:ジョブ・クラフティングの実施
課題:
従業員が自分の仕事にやりがいを感じにくく、離職率が高い。
取り組み:
ジョブ・クラフティングを通じて、従業員が自分の仕事をより魅力的に感じられる工夫をした。(例:スキル開発の機会提供、個々の強みを活かすプロジェクト参加)
成果:
従業員の働きがいやワーク・エンゲイジメントが向上し、離職率が低下した。
事例③:フィードバック文化の整備
課題:
従業員が自分の仕事に対するフィードバックを得にくく、成長意欲が低下している。
取り組み:
上司や同僚からのポジティブなフィードバックを積極的に提供する文化を整えた。定期的な評価会やコーチングを通じ、従業員が自分の強みや改善点を理解しやすくした。
成果:
従業員の成長意欲が高まり、組織全体のパフォーマンスが向上した。
ワーク・エンゲイジメントを高めるためのポイント
ポイント①:ジョブ・クラフティングの実施
内容:
従業員が自分の仕事をより魅力的に感じるため、研修や職場環境の改善などを実施。
効果:
従業員のやりがいを引き出し、モチベーションを高める。
ポイント②:自己効力感の向上
内容:
従業員が課題に対して自信を持って取り組める環境を整備。スキルアップ研修や昇格に伴う研修、コミュニケーション機会の創出。
効果:
従業員が仕事に主体的に取り組む意欲が高まる。
ポイント③:ポジティブなフィードバックの提供
内容:
上司や同僚からのポジティブなフィードバックを積極的に提供する環境、文化の整備。
効果:
従業員が仕事に誇りを持ち、成長する動機付けも強まる。
ワーク・エンゲイジメントを高める上での注意点
ワーク・エンゲイジメントを高めるための取り組みとして「エンゲージメントサーベイを実施している」という会社が増加しているようです。
しかし、エンゲージメントサーベイの結果は現状把握に過ぎず、サーベイを実施しただけではワーク・エンゲイジメントは高まりません。
また、負担感の大きな状況が継続すると、ストレス反応の上昇とともにワーク・エンゲイジメントの低下が見られますが、稀に「ランナーズ・ハイ」のマラソンランナーのように、自身のストレス状況に気付くことなく無理ができてしまう人がいます。
高負荷な状況が長期化すればそれだけリスクは高まり、ゴール直後に崩れ落ちるランナーのように、「燃え尽き症候群」に向かってメンタルがすり減っていく状態になりかねません。
ワーク・エンゲイジメントを高めていくと同時にストレス状況も合わせて確認し、バランスを取ることが求められます。
さらに、実施義務のあるストレスチェック80項目では、ワーク・エンゲイジメントについて分析をするも可能です。
ストレスチェックで、従業員のメンタルヘルスを把握しつつ、ワーク・エンゲイジメントを高めていくためのきっかけを見つけることができます。
新たなサーベイの実施にコストや時間を負担する前に、今手元にあるデータを改めて確認し直し、十二分に活用した上で不足した情報を得るための追加調査を行いましょう。