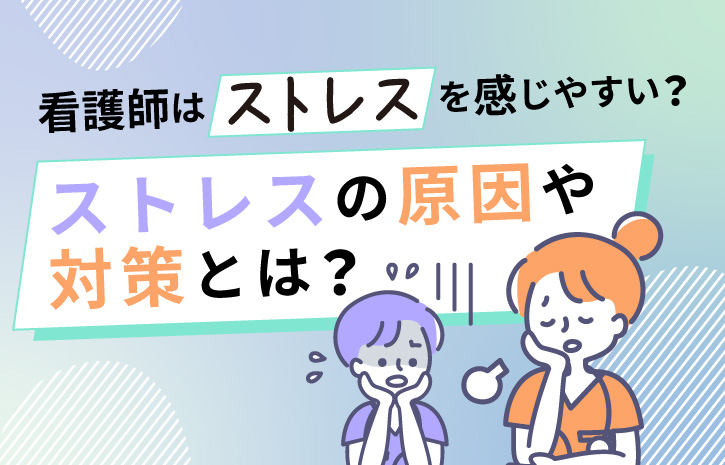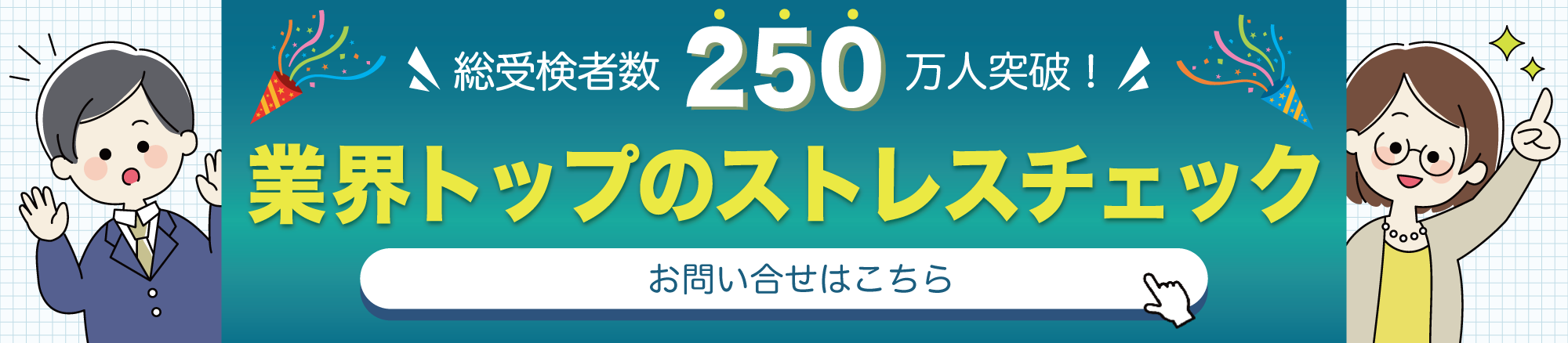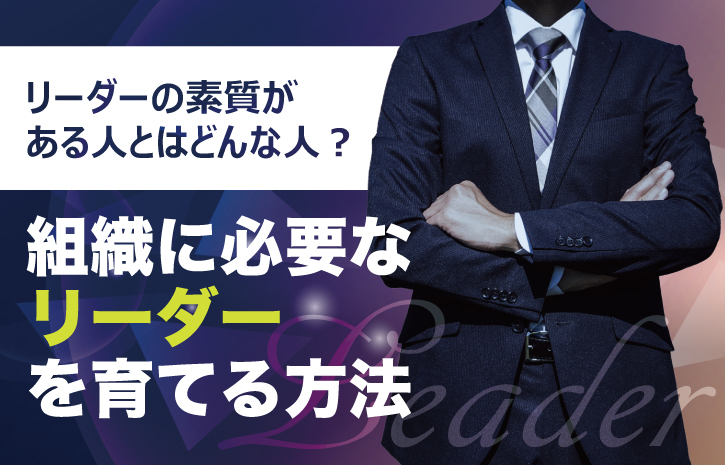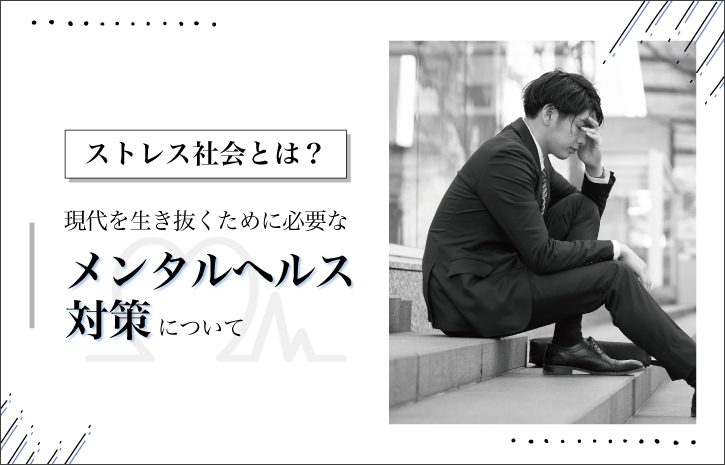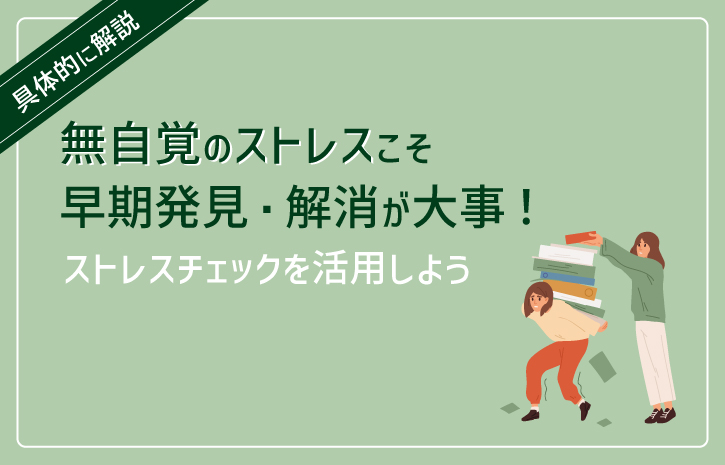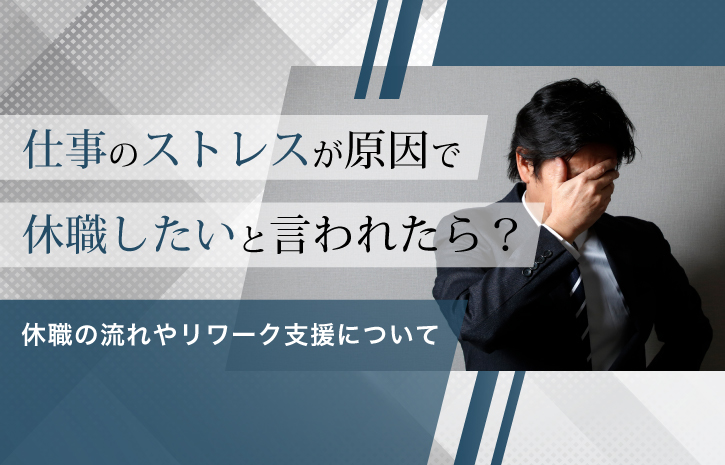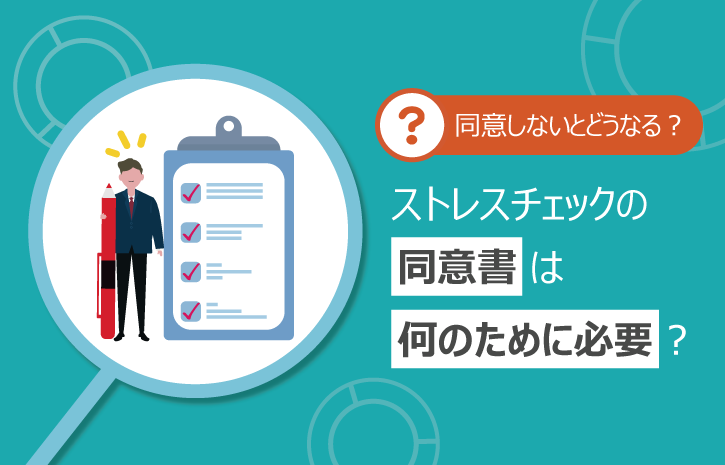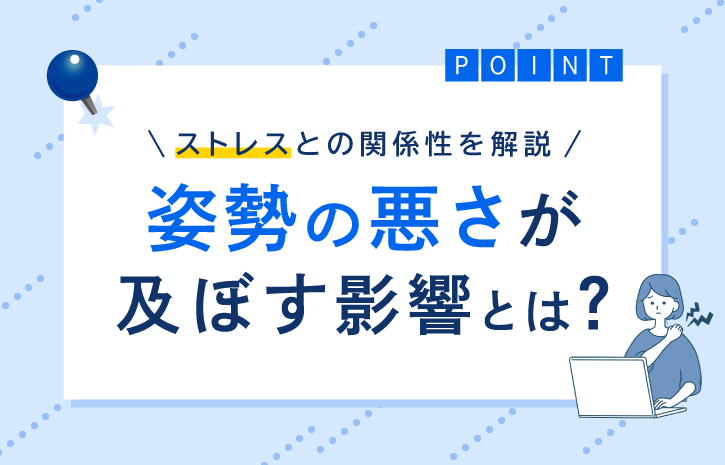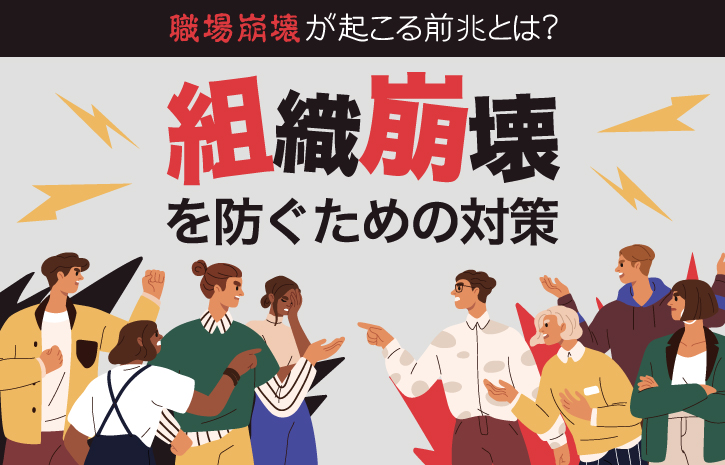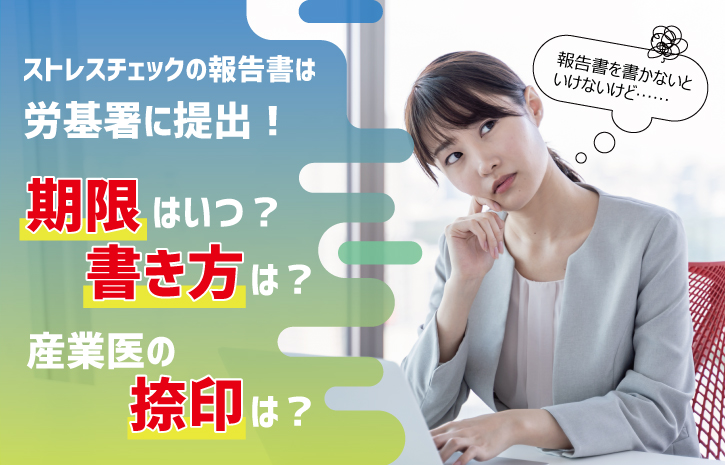看護師のストレスは、医療現場における複雑な要因が絡み合って生じる大きな問題です。
患者さんの命を預かる責任の重さ、常に緊張を強いられる職場環境、夜勤を含む不規則な勤務体制、そして慢性的な人手不足などが、看護師のストレスの要因となっています。
この記事では、看護師のストレスに着目し、その対策について考えます。
看護師のストレスはどれくらい?
2023年度のドクタートラストのストレスチェックでは、「看護師のみ」のストレスは算出できないものの、「医療業」の高ストレス者率は、15.7%となっています。
全業種の平均が15.2%であることから、全国平均と同程度の割合となっています。
しかし、看護師は業務負担の大きさなどからハイリスクグループとされており、加えて、医療業の精神障害による労災請求件数は他の業種と比較しても多いことが分かっています。
このことからも、看護師のストレスは非常に大きな問題となっていることがわかります。
看護師のストレス要因とは?
では、看護師はどのようなことで「ストレス」を感じているのでしょうか。
主な要因を以下に記載します。
業務量の多さと責任の重さ
看護師は患者さんのケアや医療処置、記録業務など、多岐にわたる業務をこなす必要があります。
また、看護師は人手不足の問題が深刻です。
こうした現状から、一人当たりの業務量増加や長時間労働の問題が発生している病院もあるでしょう。
また、看護師は、業務中は常に患者さんの状態に気を配り、わずかな変化も見逃さないようにするために緊張感が続きますし、医療ミスが許されないというプレッシャーがあるため、ストレスを感じやすい状況に置かれています。
人間関係の複雑さ
看護師は、業務上、患者さんやその家族とのコミュニケーション、医師や他の医療スタッフとの連携など、様々な人間関係の中で業務を行っています。
その中で、医師との意見の食い違い、同僚との人間関係など、人間関係の複雑さから、ストレスを感じることもあると考えられます。
不規則な勤務体制
夜勤や交代制勤務は、生活リズムを乱し、睡眠不足や疲労の蓄積につながります。
病院(病棟)によっては、休日やプライベートの時間が取りにくく、心身のリフレッシュが難しい状況です。
生活習慣は、ストレスとも関連があるため、こうした不規則な勤務体制が、少なからず、看護師のストレスに影響を与えているでしょう。
感情労働の負担
患者さんの不安や苦痛に寄り添い、精神的なサポートを行うことは、看護師にとって重要な役割です。
しかし、常に感情をコントロールし、患者さんに共感することは、精神的な負担となるでしょう。
加えて、ときには患者さんの「死」に直面するなど、仕事で感情を揺さぶられる場面も発生することもあります。
上記のような要因が考えられますが、実際に、ドクタートラストで受検した「医療業」の傾向を見ると、「仕事の質的負担」や「仕事のコントロール度」、「職場の対人関係」、「身体的負担」、「情緒的負担」などで不良な傾向が伺えます。
仕事の性質上改善が難しい場合もありますが、こうしたストレスを放置すれば、高ストレス者の増加につながることが容易に想像できます。
ストレスへの対処法
では、看護師のストレスを軽減するためには、何ができるでしょうか。
看護師がストレスを軽減するためには、職場全体での取り組みと、個人のセルフケアが重要です。
職場での取り組み
人員配置の見直しや業務分担の改善など、労働環境の整備が重要です。
しかし、人員不足の問題から改善が難しい場合もあるでしょう。
その場合は、上司や同僚からのサポートなど、ストレスを緩和する要因を増やしていただくことが重要です。
上司や同僚とのコミュニケーションを円滑にし、相談しやすい雰囲気を作るために何ができるか、上司からのフィードバックや承認が適切に行われているかなど、看護師のストレスを緩和するための取り組みを考えるのがおすすめです。
また、メンタルヘルスに関する研修やカウンセリングの機会を設けるなど、メンタルヘルスケアの充実も求められます。
周囲へSOSを出せる環境づくりも、組織の重要な役割の一つです。
個人のセルフケア
業務の性質上、大きなストレスが発生しやすい状況下で働いていることを一人ひとりが自覚し、自分のストレスをコントロールするためのセルフケアを行うことが重要です。
十分な睡眠や休息、バランスの取れた食事に留意するなどの生活習慣や、趣味や運動など、リフレッシュできる時間を持つことも大切です。
実際にドクタートラストのストレスチェックでは、「睡眠」や「飲酒」などの調査結果において、良い生活習慣を送れている人のほうが、高ストレス者率が低いことが分かっています。
看護師一人ひとりが、自分自身のストレスに向き合い、適切なセルフケアを行うことも重要と考えられます。
さいごに
看護師は、人々の健康と命を守るためになくてはならない存在です。
その貢献に感謝するとともに、看護師が心身ともに健康で働き続けられるよう、社会全体でサポートしていくことが大切です。
<参考>
公益社団法人日本看護協会
厚生労働省「令和5年度過労死等の労災補償状況を公表します」