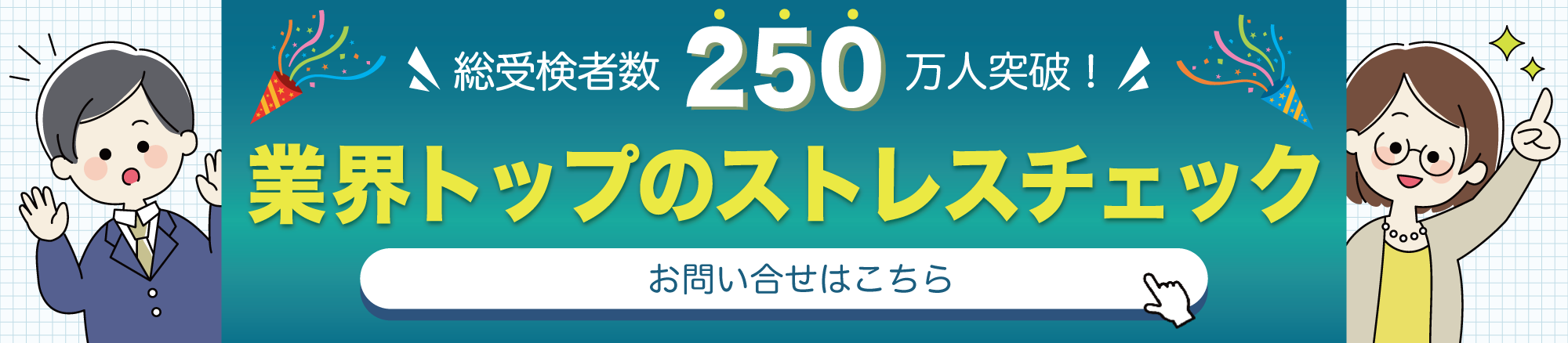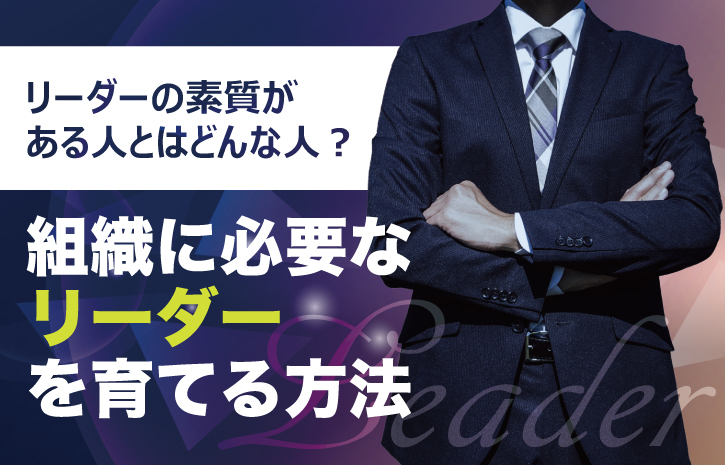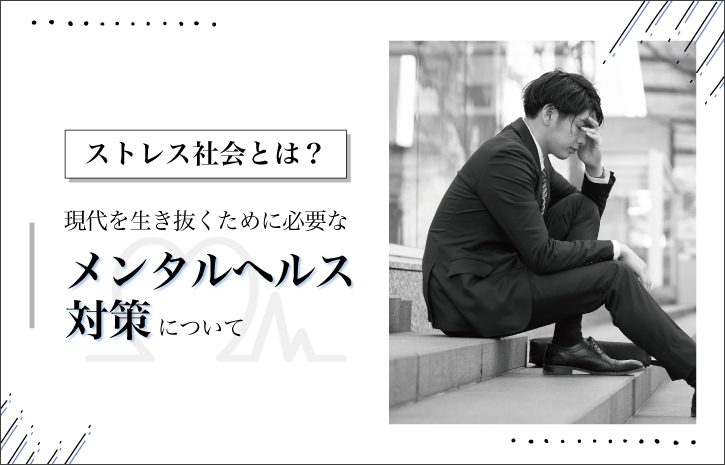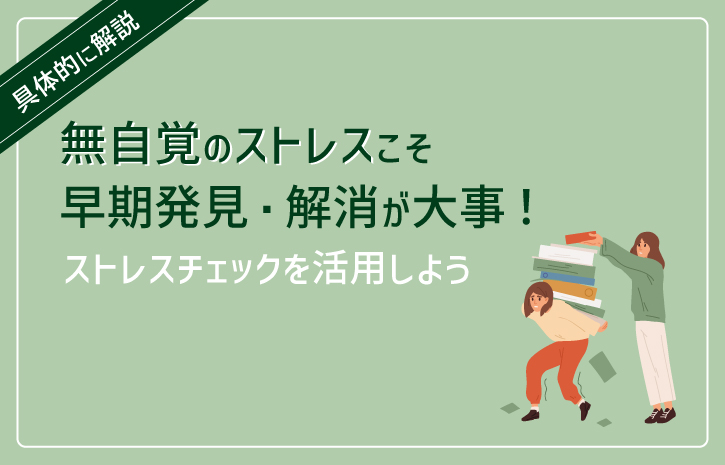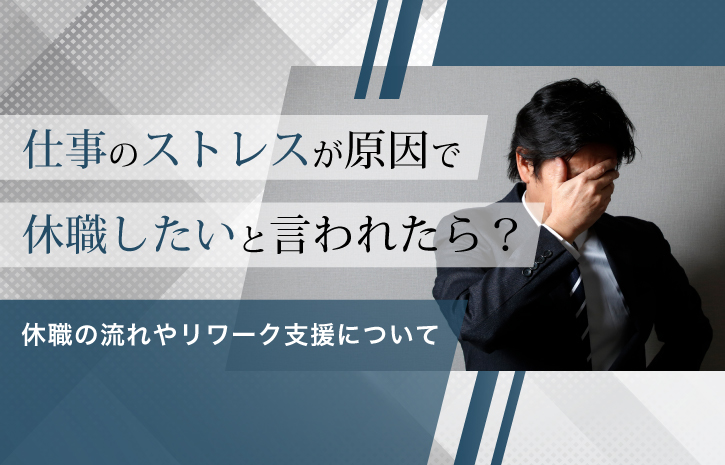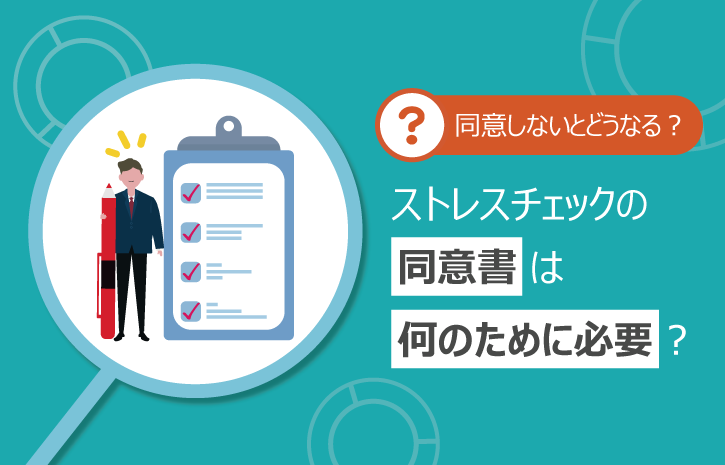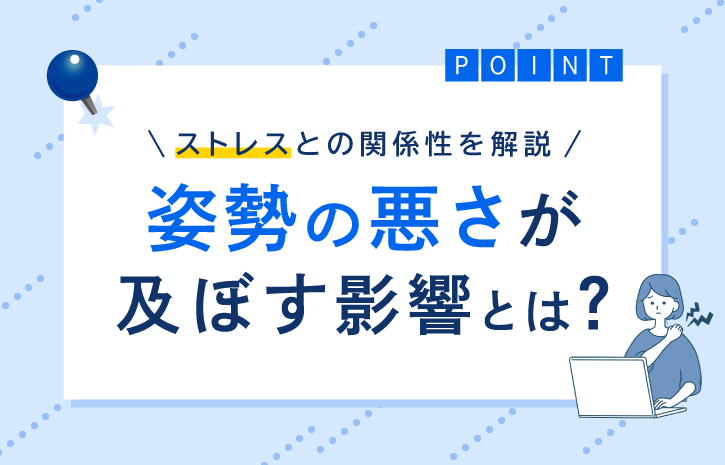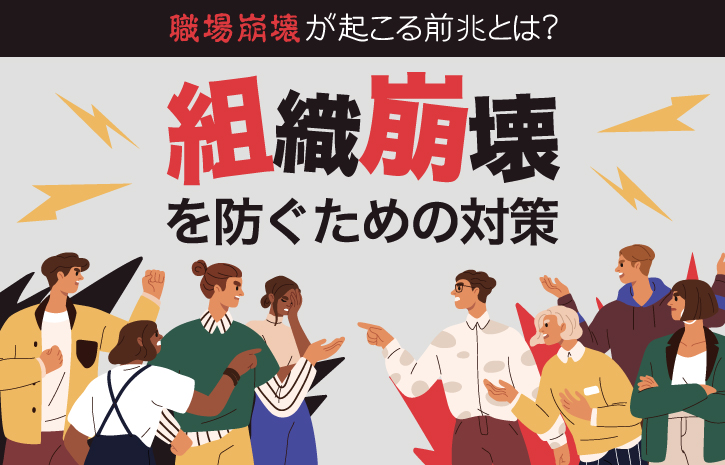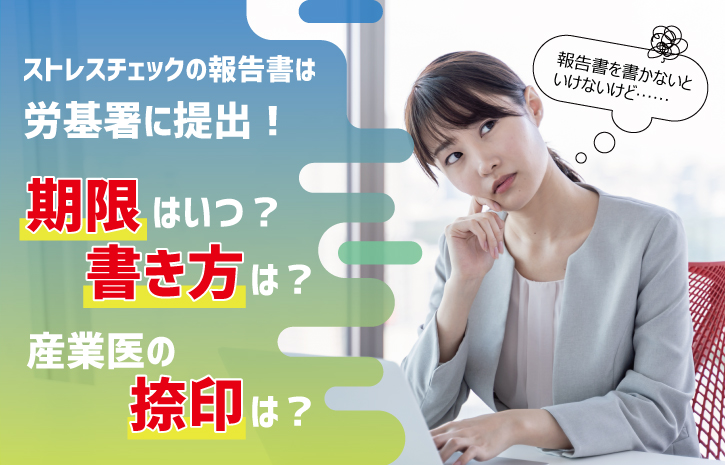現代の職場環境では、ハラスメントへの対応が会社の重要な責務として注目されています。
その背景には、労働契約法第5条や労働安全衛生法第3条に基づく「安全配慮義務」の存在があります。
本コラムでは、安全配慮義務の概要から、会社が果たすべき具体的な対応までを解説します。
安全配慮義務とは
安全配慮義務とは、会社が労働者に対して、安全かつ健康的な労働環境を提供するために必要な配慮を行う責任を指します。
この義務は、労働契約法第5条や労働安全衛生法第3条に明記されており、単なる事故防止だけでなく、心身の健康を守るための広範な配慮を含みます。
具体的には以下の内容が含まれます。
- 労働者が安全かつ快適に働ける環境の整備
- 労働災害や過重労働の防止
- メンタルヘルスケアやハラスメント防止対策
安全配慮義務違反となるポイント
会社がこの義務を果たさない場合、安全配慮義務違反として法的責任を問われる可能性があります。
違反が認定される主な基準は以下の3点です。
- 予見可能性:危険や被害を事前に予見できたか。
- 結果回避性:予見した損害を回避するための措置を講じたか。
- 因果関係:会社の不作為と労働者への被害との因果関係があるか。
例えば、長時間労働による過労死や、ハラスメントによる精神疾患が発生した場合、会社が適切な対応を怠れば、安全配慮義務違反として損害賠償責任を負うことになります。
ハラスメント対策は安全配慮義務に含まれる
ハラスメント(パワハラ、セクハラ、カスハラなど)は、安全配慮義務の一環として会社が防止すべき重要な課題です。
特に2020年以降、パワハラ防止措置が法律で義務化され、中小会社にも適用されています。
会社には以下のような「ハラスメント防止のための措置義務」が課されています。
- ハラスメント防止方針の明確化と周知
- 相談窓口の設置と体制整備
- 被害者へのケアと再発防止措置
これらは単なる形式的に措置だけをすれば良い対応ではなく、実効性ある施策として実際に運用される必要があります。
安全配慮義務違反になり得るハラスメント事案のパターン
以下は、安全配慮義務違反と認定され得る典型的なハラスメント事案例です。
ハラスメント事案①(パワハラ)
上司による暴言や過度な叱責で従業員が精神疾患を発症したケースで、相談や通報あり事実を把握していたにもかかわらず、会社して解決のために具体的な対応を行わなかった事案。
ハラスメント事案②(セクハラ)
性的言動により職場環境が悪化し、被害者が退職を余儀なくされたケースでは、相談をしたことにより被害者が意図しない異動をさせられるなどの不利益取り扱いを受けた事案。
ハラスメント事案③(カスハラ)
顧客からの暴言や脅迫を放置し、従業員が精神的ダメージを受けたケースでは、顧客からの迷惑行為が行われていることを認識していたにもかかわらず、従業員に対応を任せ放置した事案。
いずれの場合も、会社側が問題を認識しながら適切な対応を怠った場合、安全配慮義務違反として損害賠償請求などのリスクにつながります。
会社が取り組むべき対応や対策
安全配慮義務を果たすために労務管理はもちろん、法律上の義務を果たすだけではなく会社として講じるべき具体的な対策について紹介します。
1. ストレスチェック
- 定期的なストレスチェックを実施し、従業員のメンタルヘルス状態を把握するとともに、従業員にもセルフケアやラインケアの意識づけ。
- 必要に応じて産業医との面談やフォローアップを行う。
2. 職場環境改善活動
- 労働環境評価を定期的に実施し、危険要因やストレス要因を特定し、経営課題と捉え会社として改善に取り組む。
- ハラスメント防止研修やコミュニケーション向上施策などを導入とくり返しの実践による組織風土醸成。
3. 相談窓口の設置
- 社内相談窓口だけでなく、外部機関との連携による第三者相談窓口も設ける等、相談のしやすさに注力することは、結果的に情報の早期収拾を実現し会社を守ることにつながる。
- あわせて、プライバシー保護や中立性確保により、従業員が安心して相談できる体制を整えるとともに、相談や通報があった際のエスカレーションフローを明確に定め、周知する。
4. 再発防止策
- ハラスメント発生時には迅速かつ適切な調査・処分を行い、その結果を基に再発防止策を講じる。
- 被害者と加害者の双方へはもちろん、周囲へのフォローアップも欠かさない。
まとめ
ハラスメント対策は単なるコンプライアンス遵守ではなく、「従業員が安心して働ける職場環境」を提供するための基本的な責任です。
会社は日頃から使用者責任はもちろん、安全配慮義務に基づく施策を徹底し、トラブル未然防止と健全な職場文化の醸成に努める必要があります。
労働人口が減少を続ける現代の日本において、会社の安定した成長や存続のために必須の取り組みであることを認識しましょう。