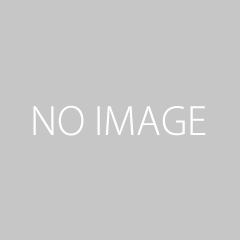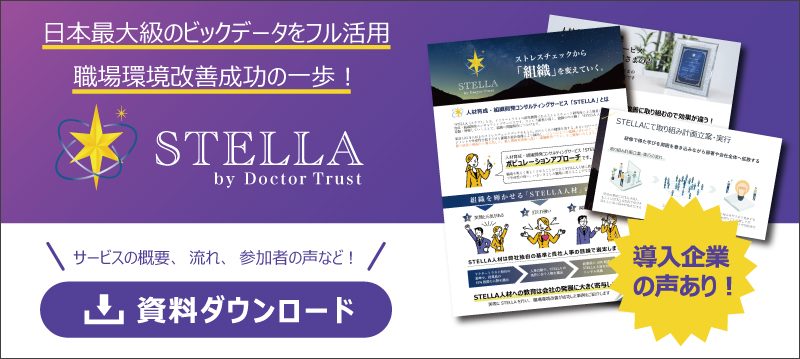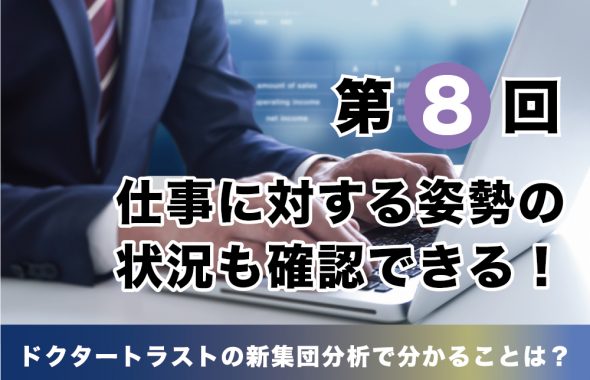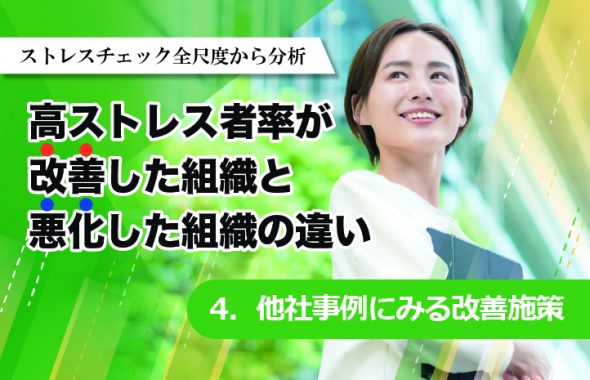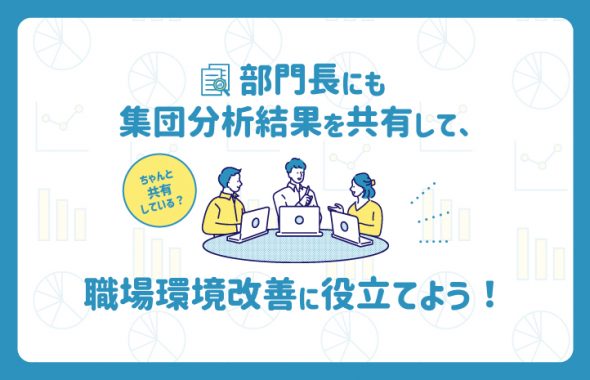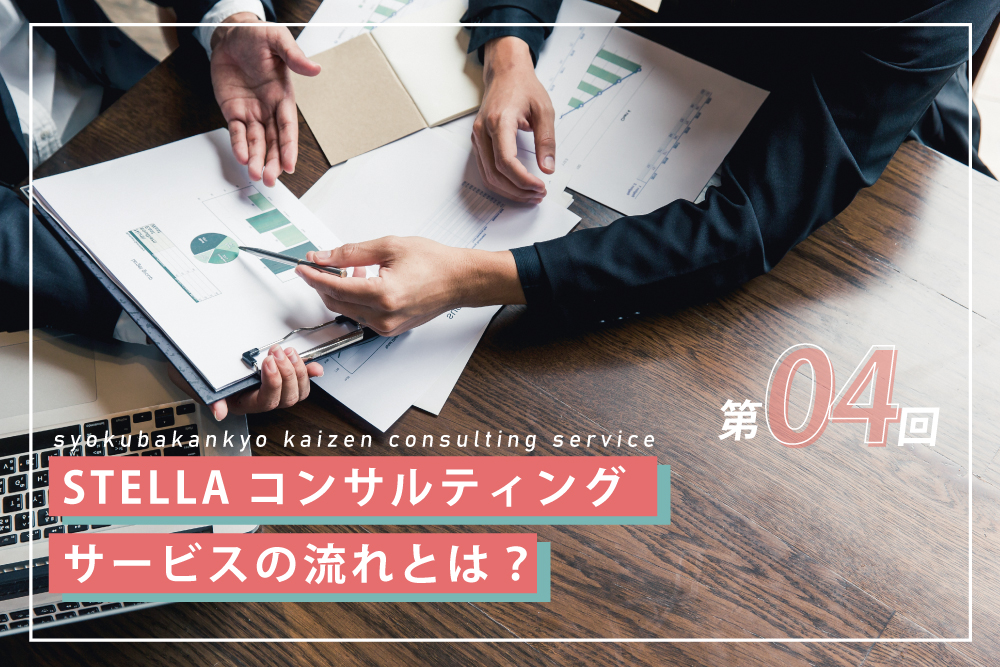
<STELLAについて徹底解説!>【第4回】STELLAコンサルティングサービスの流れとは?
最終更新日 2023-01-10
人材育成・組織開発コンサルティングサービス「STELLA」について全4回でご紹介するコラムシリーズ、いよいよ最終回です。
これまで3回のコラムの中で、健康でいきいき働き、周囲に良い影響を及ぼす「STELLA」とはどんな人材なのか、「STELLA」が多い職場と少ない職場の特徴は何か、そして「STELLA」を組織やチームで活かすポイントは何かについて、ドクタートラストでストレスチェックを受検した累計103万人のデータを交えてご紹介してきました。
最終回となる本コラムでは、実際にどのような流れでコンサルティングが進んでいくのかをわかりやすくお伝えします。
Step1.集団分析結果報告会で現状把握を行う
何を始めるにも、どこにどんな課題があるのかを知ることが重要です。
そこで、初めに経営層や人事向けに集団分析結果報告会にて、ストレスチェック結果をさまざまな角度から分析し、課題の洗い出しを行います。
なお、ドクタートラストの集団分析は毎年アップデートを行っており、今年度新たに追加された「TRUSTY SCORE」(職場環境指数)や、高ストレス者を生み出す原因分析など、累計103万人のストレスチェックデータに基づいたさまざまな分析結果が掲載されています。
下記コラムにて集団分析の詳細な説明が掲載されておりますので、ぜひ合わせてご覧ください。

Step2.STELLAを選出する
現状把握ができたら、本コンサルティングの鍵となるSTELLAの選定を行います。
どのような特徴がある人物を選んでいくのか、選定基準の例を一部ご紹介します。
【STELLA選定基準(例)】
・人から好かれる雰囲気を持っている
・周囲に影響力がある
・周囲から話しかけられやすい
・打たれ強い
・仕事が好き
・笑顔が多い
・元気がある
上記以外にも別途、会社として考えるSTELLAの要素や、ストレスチェック結果等を総合的に考慮しながら、健康でいきいき働く周囲に良い影響を及ぼす人材「STELLA」を選定していきます。

Step3.STELLAを対象にチーム内を活性化させるための研修実施
STELLAが選定できたら、いよいよ研修へ進みます。
研修ではSTELLAに効果的な学びを得ていただくため、下記3つの特徴を備えています。
【STELLA研修の特徴】
① 座学だけではなくアクティビティやグループワークが豊富
② 体験学習により学びの腹落ち感を高める
③ 学びの腹落ち感が研修後の取り組みへのコミットメントを高める
たとえば、STELLA研修のひとつにコミュニケーション研修があります。
この研修でのポイントは「コミュニケーション量を増やすこと」「相互理解を深めること」なのですが、この2点がなぜ大事なのか、座学だけで理解してもらうには限界があります。
そこで、理解促進に役立つアクティビティやグループワークを盛り込むことで、実際に身体を動かし、STELLA同士コミュニケーションを取りながら、「コミュニケーション量を増やすこと」「相互理解を深めること」の重要性を体験的に実感してもらう、といった構成を取っています。
このような特徴を備えた研修がどのように捉えられているか、実際の参加者の声を一部ご紹介します。
★☆STELLA研修参加者の声(一部抜粋)☆★
① コミュニケーション量を増やすことについての感想
・ 座学でコミュニケーションの量と質が大切と言われた時は、「どういうことか、どうしてそうなのか」ピンとこなかったが、グループワークで身をもって体験したことで、理解が深まった。
・ 言葉だけで自分が伝えたいイメージと、相手が思い描くイメージをすり合わせることが想像以上に難しく、コミュニケーションを考え直すきっかけになった。
② 相互理解を深めることについての感想
・ 普段なかなか話す機会のない人たちの新たな一面を知ることができた。
・ 他部署の人から自分がどんな人物に見えているのかを知ることができ、面白かった。逆に自分は同じ部署の人のことは知っていても他部署の人とのことはあまり知らなかったと実感する機会にもなった。
このように座学とアクティビティやグループワークを上手く織り交ぜることで学びへの理解を促進し、その後の取り組みへのコミットメントを高めています。
研修後、学びを活かした組織活性化の取り組みを行う中でお悩み等が発生した場合は、ドクタートラストにて随時相談受付やアドバイスを行います。
また、管理職の皆さまからの感想も下記コラムにてご紹介しておりますので、ぜひご覧ください。

Step4.次年度のストレスチェックで効果測定
取り組みの結果どのような変化があったか、取り組み前後のストレスチェック結果やその他サーベイ等を参考に効果測定を実施。
それらの結果を踏まえ、改めてどのように動いていくか次年度の職場環境改善計画を立案、実行と、取り組みのPCDAを回し続けていくことになります。

以上で、人材育成・組織開発コンサルティングサービス「STELLA」をご紹介するコラムシリーズは終了です。
職場環境改善を行いたいと思っていても、具体的にどんなことをしていけばいいのかわからないという企業様は少なくありません。
そんな時はぜひ、ドクタートラストにお問い合わせください。
医療職、健康経営コンサルタント、ハラスメントカウンセラーなど多種多様な専門家が培ってきたノウハウを結集し、皆さまの職場で働く人々が自らの力を最大限発揮できる環境作りをお手伝いします。
執筆者

-
【保有資格】健康経営エキスパートアドバイザー
【コメント】前職ではやりがいはあったものの、長時間労働が当たり前の環境で働く中で、ワークライフバランスについて考えるようになりました。今では健康経営エキスパートアドバイザーとして、ストレスチェック結果を活用した職場環境改善に取り組む企業のコンサルティングや、各種セミナー等を行っております。これまでの学びをもとに「健康でいきいきと働く人」を世の中に増やすために役立つ情報をお伝えします。
最新の投稿
 コラム2023-04-03ジョブ・クラフティングで自分自身の働きがいを高めよう!
コラム2023-04-03ジョブ・クラフティングで自分自身の働きがいを高めよう! STELLA2023-01-27ビジネスにおける生産性とは?生産性向上のポイントは3つ
STELLA2023-01-27ビジネスにおける生産性とは?生産性向上のポイントは3つ STELLA2022-11-29職場環境改善や生産性向上に役立つ「チームビルディング」とは?
STELLA2022-11-29職場環境改善や生産性向上に役立つ「チームビルディング」とは? STELLA2022-09-27ストレスチェックとエンゲイジメントサーベイの違い、効果的な使い方を解説
STELLA2022-09-27ストレスチェックとエンゲイジメントサーベイの違い、効果的な使い方を解説